我が家の次男は、海外で生まれ育ち、現地校で英語の中で心を育んできました。
しかし、帰国後、日本語の世界で自分を出すことができず、帰国子女としての苦しみから、不登校になりました。
この記事では、我が家の次男が経験した現地校から帰国後の苦しみと、それをどう乗り越えようとしたのかをお伝えします。
駐在を予定しているご家庭、インターナショナルスクールに通うお子さんのいる家庭、そしてバイリンガル育児に悩む家族にとって、少しでも参考になることがあれば嬉しいです。
Contents
なぜ我が家は現地校を選んだのか

駐在が決まったとき、私たちはまだ「どれくらい海外で生活するのか」さえ分からない状態でした。
だからこそ、限られた時間の中でも、子どもたちには本物の異文化や多様性に触れてほしいという気持ちが強くありました。
現地はイスラム教徒や中国系、インド系、マレー系など、多民族が共に暮らす国で、街を歩けばさまざまな言語が飛び交っていました。
でも、人々はとても温かく、子どもに優しくて、治安も比較的安定している。そんな環境だったからこそ、思い切って現地校を選べたのだと思います。
とはいえ、私たちにとって現地校は大きなチャレンジでした。
夫は英語ができても、私はまったくの初心者。先生とのやり取りやママ友との付き合い、どうしたらいいのか不安だらけでした。
勉強熱心な国だったため、子どもが英語で勉強についていけるのか?サポートできるのか?毎日が手探りでした。
長男は、最初に通った英語幼稚園で、同じクラスにいた日本人兄弟の存在に助けられて、なんとか馴染むことができました。
でも、10歳のとき、ふとこんなことを言ったんです。
「小学校に行っても、言いたいことが全部言えたわけじゃない。映画も、ちゃんと英語で楽しめるようになったのは10歳くらいからだった」
その言葉に、私はハッとしました。英語を自然に使っていたと思っていた彼にも、伝えきれないもどかしさはずっとあったのだと気づいたのです。
一方、次男は現地で生まれ、1歳半から兄と同じ英語幼稚園へ。その後はインターナショナルスクールに進学しました。
家庭では日本語で話しかけていましたが、返事は英語まじり。兄弟の会話は完全に英語。
日本のテレビは「仮面ライダー」だけは好きでしたが、それ以外は一切見ず、本や映画も全て英語。
日本語の読み聞かせも毎日していましたが、明らかに彼の脳は英語脳として育っていました。
少なくとも私には、幼稚園教諭としての経験がありました。
幼稚園でどんな体験をするのか、どんな力がついていくのかはある程度分かっていたし、だからこそ、日本語でのサポートは自信がありました。
そして何より、子どもたちが楽しそうに過ごす姿を見て、
「言葉ってこうやって自然に育っていくんだな」
と、むしろその過程を観察するのが面白く感じられるようになっていました。
英語で生きる子どもたちと家庭の言語環境
私たちは家庭では日本語で会話をしていました。
でも、子どもたちから返ってくる言葉は、自然と英語まじりに。特に兄弟同士の会話は、完全に英語でした。
長男は幼稚園から英語環境で育っていたとはいえ、日本語での会話にもそこまで抵抗はなく、本人の中では自然に切り替えができていたように思います。
一方、現地で生まれた次男は、日本語よりも英語のほうが「本音」を話しやすい子でした。
読み聞かせは毎日していたし、日本語でたくさん語りかけもしてきました。
でも次男にとっては、言葉だけでなく“世界そのもの”が英語だったのだと思います。
映画も絵本も、お気に入りのアニメも英語。
本を読むのも好きでしたが、それもすべて英語。
日本語のテレビ番組には興味を示さず、「仮面ライダー」だけは唯一好きな日本語コンテンツでした。
興味のあること、嬉しかったこと、悲しかったこと――
そんな日常の感情を英語で表現し、英語で受け止められてきた彼にとって、「英語=心のことば」になっていたのだと思います。
そしてそれは、後に彼が“日本語の世界”でつまずいたとき、私たちがあらためて気づかされることになるのです。
コロナがすべてを変えた。予定外の突然の帰国
私たち家族は、子どもたちが高校を卒業するまではアジア各国を転々とするつもりでいました。
けれど、コロナがすべてを変えました。
世界中がパンデミックに揺れる中、私たちの滞在していた国でも、入国制限やビザの更新条件が急変。
特に「ワクチン未接種者へのビザ発給停止」が決まり、接種を望んでいなかった私たちは、ビザを失う=その国に住めなくなるという状況に直面しました。
もはや「帰るかどうか」ではなく、「帰るしかない」という選択。
そうして、予定よりずっと早く、日本への帰国を決めました。
帰国後は、夫の実家のある地方都市へ。
そこにはインターナショナルスクールなどの選択肢はなく、次男は4年生として地元の公立小学校に通うことになりました。
現地では毎日、スクーターに乗って友達と学校へ行き、放課後はすぐに遊びに出かけるような、活発で人懐っこい子だった次男。
「学校休みたい」なんて一度も言ったことがない子が、まったく違う環境に放り込まれたのです。
公立小学校で始まった“違和感”

地元の公立小学校に通い始めた次男は、最初こそ新しい環境に戸惑いながらも、なんとかがんばって通っていました。
でも、日が経つにつれて、少しずつ“違和感”が表に現れてくるようになりました。
英語で心を開いていた彼にとって、日本語での人間関係はまるで別世界。
日本語を「話せない」わけではない。
でも、「どう返すのが正しいのか」「どうふるまえば笑われないのか」がわからない。
その不安が、彼の中に静かに積もっていったのだと思います。
学校で「笑い方が変だ」とからかわれたこともありました。
自分の言葉や表現が、どこか浮いてしまう。
そしてそれが、自分でも気づかないうちに、**「自分を出すこと=間違えること」**という感覚に結びついていきました。
どんな返答をすればいいのか常に考えてしまい、間違った反応をして笑われるのが怖くて、どんどん笑顔が消えていく。
「日本語の中にいるときの自分」と、「英語の中にいるときの自分」は、まるで別人のようだったのかもしれません。
それでも最初の1年ほどは、先生にも恵まれ、遅刻しながらも通えていました。
でも、次第にそのバランスも崩れていきます――。
笑顔が消えていった理由──次男に起きた心と体のSOS
次男の様子に、少しずつ「これまでとは違う何か」を感じ始めたのは、帰国から数ヶ月が経った頃でした。
学校から帰るとどっと疲れたような顔をして、口数も少なくなる。
「今日はどうだった?」と聞いても、返ってくるのは曖昧な返事ばかり。
そしてある日、彼の目の瞬きが止まらなくなったことに気づきました。
小刻みにまばたきを繰り返す、チック症状でした。
さらに、お腹が痛いと訴える日が増え、朝になると「行きたくない」と言い出すように。
それでも、彼はがんばって登校を続けていました。
「学校を休んでもいいよ」と伝えても、「行かなきゃダメなんでしょ」と、自分を押し込めていたように思います。
学校では「笑い方が変だ」と言われ、友達ができない。
話しかけても、どう返せばいいのかがわからない。
間違った返答をしてまた笑われることが怖くて、言葉を発すること自体にブレーキがかかっていったのかもしれません。
もともと明るくて人懐っこく、すぐに打ち解けて友達をつくっていたあの子が、笑顔をなくしていく。
あの姿を見て、私はようやく「これはただの“環境の違い”では済まされない」と強く思いました。
「どうやったら好きになってもらえるの?」と聞かれた日
不登校になる直前、次男は6年生になっていました。
これまでの先生とは違い、6年生の担任との相性がどうしても合いませんでした。
家ではほとんど学校のことを話さなかった彼が、ある日ぽつりと、こんなことを言いました。
「ママ、どうやったら僕のこと、先生に好きになってもらえるの?」
その言葉を聞いた瞬間、胸が締めつけられるような気持ちになりました。
どれだけ頑張っても、自分を否定されているように感じていたんだ――と。
自分の振る舞いを変えて、“好きになってもらえるように”努力しようとするなんて、どれだけ追い詰められていたのか。
私は、もう十分だと思いました。
「しんどかったね。好きになってもらうために、自分を変えなくていいよ。あなたはとても優しくて、何も間違っていない」
そう伝えると、彼は少し黙って、そして静かに言いました。
「もう、日本の学校には行かない」
こうして、次男の不登校が本格的に始まりました。
でも、私たちにとってそれは、「負け」ではなく、大切なものを守るための選択でした。
今、私たちが大切にしていること

「学校に行かない」という選択をしたあと、次男は少しずつ表情を取り戻していきました。
チック症状も自然とおさまり、言葉も、笑顔も、ほんの少しずつ戻ってきました。
私たちはあらためて、“学校に行く”ことよりも、“心の安全”のほうが大事なんだと気づかされました。
無理して適応させるよりも、その子が安心できる場所で、自分らしくいられること。
それが何よりも大切だと、今は思っています。
もちろん、不安がゼロになったわけではありません。
でも、「無理に社会に合わせなくてもいい」と思えるようになってから、私たち親子の関係はもっと柔らかく、もっと正直になった気がします。
今の次男は、少しずつ「自分のペース」で外の世界とつながり始めています。
学校ではない形での学びを取り入れたり、安心できる大人や友達と出会えたり。
少しずつ、彼なりのリズムで世界を広げようとしているところです。
日本語に触れる機会が少なかったことへの反省
海外で生活していた頃、私たちは家庭内で日本語を使ってはいました。
読み聞かせもしていたし、日本語で会話する時間も意識的にとってきたつもりでした。
それに、日本語補習校にも通っていました。
けれど、今思えば、日本語で“心から通じ合える相手”が身近にいなかったことが、何よりも大きかったのだと思います。
日本語で話す機会はあっても、安心してその言葉を交わせる相手がいなかった。
それが、次男の中で「日本語=自分を出せない言葉」になってしまった一因だったのかもしれません。
英語では感情をスムーズに表現できるのに、日本語になると戸惑いが生まれてしまう。
自分の気持ちをどう言えばいいのか分からず、返答に迷ってしまう。
それが人との距離感やコミュニケーションに影を落としていたことに、帰国してから気づきました。
日本語の学びをもっと「伝える言葉」としてサポートしてあげられていたら――
そんな反省も、今の私たちの中にはあります。
けれど、だからこそ今は、日本語と英語の両方で“自分を表現できる場”をつくっていくことを大切にしています。
英語でも日本語でも、どちらでも「自分らしくいられる」ように。
それが、これからの次男の人生にとって、きっと大きな力になると信じています。
まとめ

海外で育った子が、日本語の中で苦しむ。
それは、単なる言葉の問題ではなく、帰国子女としての心の居場所の問題かもしれません。
今回は、我が家の次男が現地校から帰国後に感じた苦しみと、その後の歩みをお伝えしました。
同じように帰国後に不登校を経験している子どもたちに、少しでも希望を届けられたらと思っています。
次回は、長男の英語習得の道のりや、バイリンガル育児の落とし穴についてお話しします。
「子どもはすぐに英語を覚える」と思っている方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
無理のない学び方、子どもの個性に合った環境、そして“ことば”と“心”のつながりについて――
これからも少しずつ、我が家の体験を綴っていきます。
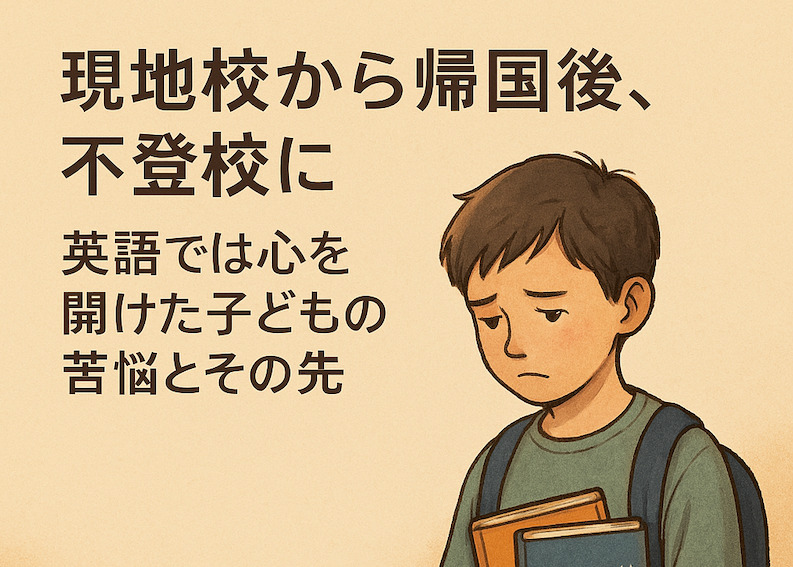
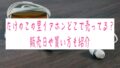
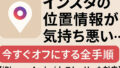
コメント